モビリティ分野のパイオニア
パデコの創業セクターは交通計画であり、1980年代の創業時から現在までモビリティの分野のユニークな存在であり続けています。パデコがどのようにモビリティ分野でのイニシアティブをとり続けてきたのか、紹介したいと思います。
「ペダルを踏み込む価値」は幾らなのか? 世界銀行 - NMV調査 1995年
パデコの特徴ある業務経験としては、1995年の世界銀行NMV(Non-Motor Vehicle)調査が挙げられます。当時は、途上国でも自動車普及・道路整備が進み、それに伴う交通渋滞が目立つようになった時期です。実際の交通状況を見てみると、一般市民の自転車利用、シクロによるタクシーサービス、動物による牽引(馬車や牛車)運搬、つまり、非駆動機関ベースの車両(NMV)による交通・運輸サービスが引き続き存在していました。また、道路整備は自動車利用に基づく便益(渋滞緩和、所要時間削減など)だけが計測され、NMVのコストや便益が評価されておらず、その結果、自動車専用道路の整備が優先される傾向にありました。
パデコは世界銀行交通部門と一緒に、東南アジア、南アジアの特徴あるNMV運用に関して、車両の初期コスト、運行コスト、運用実態、事業形態などの調査を進め、定量的な評価が出来るような数値データを取り纏め、WBの標準的な道路投資評価プログラムであるHDM-III(2000年以降は「HDM-4」に改訂)に評価モデルとして組み込みました。この結果、道路投資評価において、NMV利用の多い街路や地方道路への投資が正当に評価されるようになりました。
世界銀行やアジア開発銀行、JICA、各途上国政府が整備する都市内道路、都市間道路事業はHDM-4で事業分析することがデファクト・スタンダードになっていますが、この事業分析手法に、末端のモビリティであるNMVが組み込まれ、現在の持続的なモビリティ確保の先鞭となったのは、パデコのこの調査だとも考えられます。
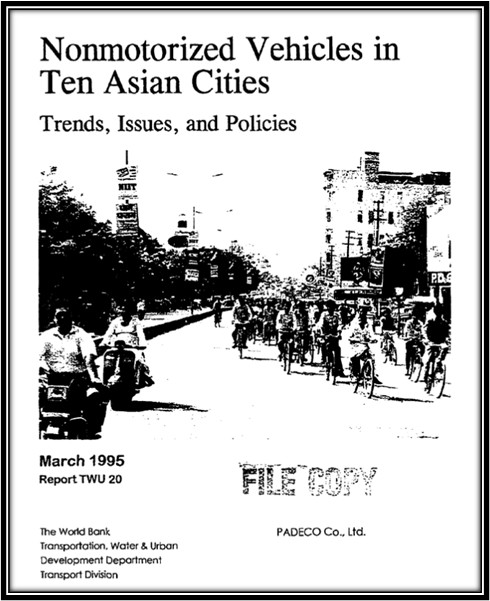
世界銀行のアーカイブにあるNMV調査レポート(1995年)、白黒の写真でスキャンも余り良くないが当時の貴重な資料
日本の経験を世界に繋いだパイオニア~WB有料道路調査、WB都市交通調査
1998年から2001年にかけて、世界銀行(WB)・交通部門、本邦の建設省、運輸省(当時)とともに、日本やアジアのインフラ整備知見を各国で共有し、更なるモビリティ整備を進めるために、当時最先端のインフラ整備状況を横断的に調査する業務を実施しました。1998年から99年に実施された「WB Toll Road Study – Asian Crisis」は、丁度アジア通貨危機の時期に重なり、民間資金を活用した道路整備(色んな言い方はありますが、PPP・PFI、BOT、DBFOによる道路整備など)が次々と頓挫していく中で、どのように持続的に「有料道路」というスキームが形成されるべきなのか、東南アジア、欧州、南米からの専門家を集めた討議を主催しました。
また、2000~01年にかけて、日本の都市鉄道、都市交通の整備スキーム、資金確保策、知見を包括的に解説したのがWB Urban Transport Strategyです。東京、名古屋などの大都市だけではなく、浜松、高松などの中都市の都市交通整備の経緯、政策、資金確保策を詳細に説明しています。また、支払メディアの趨勢、騒音・環境負荷低減策などについても解説しました。
パデコは2020年以降も引き続きこのようなモビリティ、交通インフラ整備に関する提案や事業支援を行っていますが、この2つの調査に代表されるように日本の優れた知見・経験を如何に現地にFitさせるかと言う視点に立って、提案を組み立てています。
交通マスタープランや計画マニュアル策定
モビリティ計画の基本となるのが交通マスタープランです。パデコは様々な地域や都市を対象に交通マスタープラン作りに取り組みました。例えば、80~90年代の大メコン地域(ADB/JICA)、ウルムチ(WB)、2000年代に入ってブカレスト、チェンマイ、コロンボ(JICA/ADB)、コルカタ、アレキパ(IDB)、2010年代に入ってタンザニア物流、マプト、撫州(WB)、吉安(WB)、モンバサ、ナイロビ、ダッカ周辺都市群、2020年代では、インドネシア5都市、大カイロ都市圏、など、世界中に及んでいます。また、JICA技術協力による業務だけではなく、世界銀行、アジア開発銀行、米州開発銀行など海外ドナーからの業務実施経験が積み上がっているのもパデコの特徴です。
マスタープランの作成業務は、パデコのコンサルタントが直接計画作りに携わるものですが、現地政府がその国の基準に従って自身でマスタープランを策定するためのガイドラインやマニュアル作りにも関わります。インド政府住宅都市省・ADBをクライアントとしたインド都市交通戦略業務では、インドの50万~400万人規模の都市を対象としたバスやBRT導入のための中規模都市のための都市交通整備マニュアルを作成しており、現在でも活用されています。
モビリティのラスボス、メトロ整備
色々と議論はあるかもしれませんが、現代社会において究極のモビリティ整備とは「メトロ整備」であると言えます。タクシーやバス、道路整備、駐車場整備から始まり、歩道ネットワーク、トラム、BRT、都市高速道路などの検討を経て、最終的にメトロ(高架鉄道・地下鉄)などの整備が俎上に載ってきます。非常に高額の整備費用と資金確保プレッシャー、10数年にも亘る整備期間、大規模な運営組織の必要性、火災・事故対応の研究、など検討内容が多く、また、どの国においても「初めての都市地下トンネル建設」、「初めての5分間隔の鉄道運行」など、初めての事業が伴います。
パデコは2004~2010年にソフィアメトロ延伸事業GC(2.8km、ブルガリア初のTBM導入)、2012~14年のジャカルタMCSプロジェクト(メトロ公社であるMRTJ社新規設立業務)、2014年~2019年のジャカルタメトロ1号線整備事業GC(14km、インドネシア最初の地下鉄整備)、2015年から継続しているムンバイメトロ3号線(全線地下33.5km、27駅、ムンバイで最初の地下鉄道)、2012年から継続しているブカレスト空港アクセス線事業GC(全線地下、14km、12駅、最初の外国資金を用いたメトロ建設)、2023年開始のデリーメトロ第4期GC(優先路線3路線)など、このモビリティの「ラスボス」退治に取り組んでいます。

ブカレスト空港アクセス線事業(メトロ6号線建設現場、Tokyo駅構内、2機目のTBM発進、2025年5月)